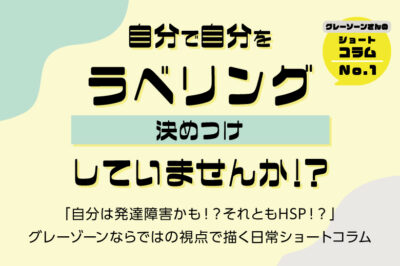「生きづらさ」とは、なんだろう?
「生きづらい」という言葉は、発達障害当事者の取材をしていると、特に多く耳にし、目にする言葉です。
当事者である私たちは、その「生きづらさ」を身をもって知っていて、「ああ、それはわかる」と心当たりのある場面がいくつも浮かびます。
だからこそ、感覚的には、その言葉の意味を理解できているような気がしています。
けれど、いざ
生きづらいとは、どういう状態なのか?」
と説明しようとすると、簡単には言葉にできないように思うのです。
発達障害がある人、精神疾患を抱えている人、ひきこもりの経験がある人、社会にうまく適応できなかった人。
そこにはそれぞれ異なる困難やトラウマ、過去があり、一つの言葉で括るには、あまりにも多様な背景があります。
当事者の特性そのものを指して「それが生きづらさの正体だ」と語られることもありますし、本人ではなく、環境や社会に原因があると説明されることもあります。
また、ネガティブな状態から語られる「生きづらさ」は理解されやすい一方で、「優秀すぎるがゆえに生きづらい」という話も、確かに存在しています。
ここまで考えてみると、「生きづらい」という言葉が、いかに幅広く、そして輪郭をつかみにくいものかが見えてきます。
やはり、「生きづらさ」とは何なのかを一つの定義にまとめること自体が、とても難しいのだと思います。
だからこそ、この言葉は、簡単に消費されてはいけないのではないでしょうか。

一通のメッセージから始まりました
2025年12月の末。
以前『凸凹といろ。』で取材した八柳まごいちさんから、一本のメッセージが届きました。
【第二号に掲載されたまごいちさんの記事はこちら】
それは取材相手としてではなく、「一緒に何かをつくる側」としての依頼でした。
内容は、以前から構想されていた「生きづらさ」を題材とした舞台と、その制作背景を追うドキュメンタリー『プロジェクト ヒバリ』が始動した、という報告。
そして、映画への出演や、プロジェクトへの助言、アフタートークへの登壇をお願いしたい、というものでした。
舞台をつくり、さらにその制作過程を映画にするという二軸の構想は、「表現としては少し大変そうだなあ……」とも思いました。
けれど、まごいちさんの言葉から伝わってくる「とにかく動き出した」という熱量に、まずは一度、話を聞いてみようと思ったのです。
以前の記事で、まごいちさんのことは、「不登校」をテーマにした映画をつくった人として紹介しました。
でも今回は、「生きづらさ」そのものを正面から扱うといいます。
どのように迷い、揺れながら作品にたどり着くのか。
そのプロセスごと残そうとしているのだと、私は受け取りました。
混乱と、率直な言葉が並ぶミーティング
先日、この企画の最初のミーティングが行われました。
そこにあったのは、「こういう作品をつくります」という明確な完成図ではありませんでした。
代わりに並んでいたのは、たとえばこんな問いです。
- 生きづらさとは、そもそも何なのか
- 舞台を見て感動して終わるだけで、本当にいいのか
- 当事者ではない人は、どうやって「わからなさ」と向き合えばいいのか
企画者であるまごいちさん自身も当事者で、だからこそ何度も立ち止まり、「これでいいのだろうか」と問い続けていました。
舞台演出の小林さんは、こんな話をしてくれました。
「共感は、必ずしも理解と同義ではない。
悲しんでいる人を見て悲しくなるのは、あくまで間接的な感情です。
だからこそ、観客が“同じ景色を体験する”演出を考えたい」
「かわいそう」「わかる」という安全な距離を壊し、観客自身を当事者のままならなさの中に置く。
その考え方は、この企画全体が目指している方向とも重なっているように思いました。
一方、ドキュメンタリーを撮る今井監督は、まごいちさんの様子を見て、こう言いました。
「結局、これは八柳まごいちの物語やな。
彼が何を求めて、どう足掻くのか。
そのプロセスそのものを撮らなあかん」
当初は、制作に関わる当事者・協力者(出演や助言を求められた側)の活動を追う案もありました。
けれど、話を重ねるうちに、企画の重心が少しずつ変わっていったのを感じました。
見切り発車の「当事者らしさ」
正直なところ、いまだにまごいちさんが最終的に「何をしたいのか」は、はっきりとは見えていません。
そして、「何を撮りたいのか」も、同じように明確ではありません。
けれど、この「答えの出なさ」や、見切り発車のような感覚こそが、生きづらさというテーマを扱う難しさを、そのまま映し出しているように感じました。
発達障害という特性を抱えて生きることは、常に正解のない問いと向き合い、迷いながら進むことの連続でもあります。
まごいちさんが見せている混乱や立ち止まりは、彼自身が当事者として生きてきた時間の延長線上にあるものなのだと思います。
整いすぎていないからこそ、そこには無理のない誠実さがある。
私は、そんなふうに受け取りました。
それぞれの立場で、それぞれの感覚を持ち寄り、点のように散らばった違和感を、少しずつ線でつないでいく。
当初は「外から取材する」形だったものが、いつの間にか、
「一人の人間の内側に深く潜っていく」構造へと変わっていました。
私たちは当事者としての感覚を共有し、言葉や違和感を投げかける。
それを受け取ったまごいちさんが、悩み、立ち止まり、舞台や台本に反映していく。
その連鎖そのものが、このドキュメンタリーの核になっていくのだと感じています。

だから、この連載を始めます
完成されたメッセージを届ける映画ではなく、問いを抱えたまま進んでいく過程を残す映画。
今のところ、この企画は、そんな危うさと実直さを併せ持った方向を向いています。
この連載では、映画と演劇という二つの作品が生まれていく過程を、内部から当事者の視点で追いかけていきたいと思います。
- 「生きづらさ」を題材として消費しないとはどういうことか
- なぜ「感動して終わり」にしたくないのか
- 表現は、どうやって実際の生活と地続きになっていくのか
明確な答えは、すぐには出ないかもしれません。
それでも、考え続けること、立ち止まりながら進むこと。
そのプロセスを記録することに、私は意味があると思っています。
安易な共感に回収されず、それでも誰かの生活に触れていく表現とは、どんなものなのか。
その伴走を、ここから始めます。

今回の登場人物:
八柳まごいち(とまりぎクリエイターズ)
数学の中学校の講師、通信制高校の教員を経て放課後等デイサービスの児発管として発達特性や不登校傾向のある子どもたちの支援を行う傍ら、とまりぎクリエイターズの代表として舞台企画・脚本を中心に表現に携わる。 取材を軸とした企画や脚本に定評があり、原作、プロデューサーを務めた不登校を題材にした映画『絆王子』は映画祭で複数受賞し海外上映を果たし、支援者や当事者による上映会や教育・福祉職員への研修会と幅広く使われている。
小林誠司(劇団まっコイ)
兵庫県尼崎市を拠点に活動する俳優。代表を務める劇団まっコイの公演では主に演劇の演出を行っている。
他者が書いた脚本に対して作者と異なる視点から作品を分析して創作するスタイルを好む。
演じる俳優と対話を重ねながら登場人物の感情を繊細に扱うことを重視しており、近年ではメタ構造演出やオブジェクトシアターのような手法も取り入れて、目には見えない『心』の存在を観客に伝える手法を発展させている。
今井いおり(ちょもらんま企画) /ちょもらんま企画代表/映画監督
主な作品:
安もんのバッタ」中之島映画祭グランプリ・「ろまんちっくろーど~金木義男の優雅な人生~」・「調査屋マオさんの恋文」 東京ドキュメンタリー映画祭2019グランプリ
次回予告:八柳まごいちと「二つの軸」
次回は、企画者である八柳まごいちさんを迎え、
なぜこの企画を映画と演劇という二つの軸でつくろうと思ったのか、その背景をじっくり聞いてみたいと思います。
言語化できることも、できないこともある。
言葉にならないからこそ大切にしたい感覚の奥に、少しだけ踏み込んでみます。